冬の農場で少女が見たものは、死んだ子ヤギでした。深いショックを受けながらも、農場で1日を過ごすうちに、生も死も受け入れ、いのちに向き合うことを学んでいきます。
冬の北海道が舞台のいのちの物語
今回ご紹介するのは、北海道出身で北海道を舞台とした作品を数多く手がけた児童文学作家、加藤多一さんの児童小説「子っこヤギのむこうに」です。
小学4年生のマユは、札幌のおばあちゃんの家に泊まりに来ています。母さんが先に帰る予定でしたが、吹雪のため、飛行機が欠航になってしまいました。
そんなとき、母さんの古い友人ユミコさんから、子ヤギを見に行こうと誘われます。ユミコさんの車で出かけたのは、ユミコさんと母さんの同級生、斉藤さんの「大きなかぶ」という農場でした。
斉藤さん一家に会う前に、小屋にいる子ヤギに会いに行こうとしたマユたちでしたが、そこで見たのは、思ってもみなかった光景でした。マユが抱っこしようと楽しみにしていた子ヤギが、血を流して死んでいたのです。
倉庫に住んでいる斉藤さん一家に会ったマユたちは、子ヤギが犬に殺されたのだと知ります。子ヤギは雪に埋めてあったのですが、キツネに掘り返されてしまったのだろうとのことでした。
斉藤さんには、小学2年生のノブくんという息子がいます。動物たちに水を配るノブくんを手伝うマユ。そこで、死んだ子ヤギにそっくりな子ヤギがいることを知ります。
斉藤さん一家と過ごすうちに、マユは、いのちといのちとのつながりや、自分たちもいのちをいただいて生きていることを学びました。
「大きなかぶ」を後にする頃には、マユは子ヤギの死を受け入れることができたのでした。
いのちの誕生と死に向き合う
主人公のマユは、子ヤギの死というショッキングな場面に遭遇します。それも、抱っこできると楽しみにしていた子ヤギの無残な死です。
死んだ子ヤギの様子は、言葉少なくシンプルに描かれていますが、その分無駄がなくリアルに目の前に迫ってくるようです。子ヤギを目にしたマユが受けた衝撃を、読者である私たちも体験します。
マユの心にわき上がってくるのは、「かわいそう」ただその思いだけでした。
子ヤギは、生まれてすぐ、まだ体がぬれているのにもかかわらず、立ち上がり、母ヤギのおっぱいをさがすほど元気でした。元気すぎて、仕切りの隙間から飛び出し、犬に噛みつかれてしまったのです。
母ヤギは、もう一頭の子ヤギを生んでいました。後から生まれたその子ヤギは、体が弱く、なかなか自分の力で立てなかったと言います。生き残ったのは、その体の弱い方の子ヤギでした。
マユは、そのことをノブくんから聞いて知ります。
いのちは関わり合って生きている
マユたちは、斉藤さん一家と昼食を共にしました。スープやパン、野菜などの他にソーセージを焼いて食べます。マユが知っているソーセージより、ずっとおいしいものでした。
ソーセージの原料となる豚は、農薬の少ないエサと農場の草や木の根を食べ、走り回って育ったのだと言います。その豚肉を使って、添加物を加えずに、町の加工センターを借りてソーセージを作るのです。
昔はみな、豚を自分の家で殺して肉にしていたと話す大人たち。ユミコさんは、「本当は、死んだ子っこヤギをみんなで食べてあげたほうがいい」と言います。それを聞いたマユは、外へ飛び出してしまうのですが、そこで雪原に立つ不思議な木を目にします。日の当たる部分と影の部分の色が大きく異なり、まるで別々の木がくっついているように見えたのです。
マユを追ってきたユミコさんに「ソーセージは、豚を丁寧に殺してくれた人がいたから食べられる」のだと聞かされるマユ。「いのちをいただくこと」「いのちに感謝すること」を知り、心がほぐれていくのでした。
いのちをいただくということを、現代を生きる私たちはよく理解していないかも知れません。肉は、スーパーに並んだ切り身がほとんどで、元の姿を想像することは難しいくらいです。そのような状態ですから、その肉が何を食べてどのような環境で育ってきたのかすら、知りません。
マユを通して、私たちは「食」というものについて、深く考えさせられます。
少女を成長させた冬の1日の出来事
子ヤギの死を見てしまったマユの衝撃は、どれほどのものだったでしょう。大人でもショックを受けるような光景です。
それでも、現実はマユの心に糧となる何かを残したに違いありません。知り、感じ、そして考えることが、少女を大きく成長させたのではないでしょうか。
子ヤギを殺したのは、気性の荒いショウマという犬でした。斉藤さんが友人から引き取った犬です。ショウマは、「大きなかぶ」の他の犬たちになじめず、うなってばかりいたのだと言います。少しでも穏やかになれるようにと、ヤギやヒツジと同じ小屋で暮らすようにしていました。結果的に、子ヤギを殺してしまうのですが、マユが驚いたのは、ノブくんがショウマを憎んでいないことでした。
食事の後、ユミコさんを中心に、死んだ子ヤギとお別れをします。雪を盛り上げて作ったテーブルに子ヤギを乗せ、両手を合わせてお祈りをしました。
そして、子ヤギをそのままにして、その場を後にします。「みんなに食べてもらえばいい」それがユミコさんの考えでした。斉藤さんも言います。「冬の間、食べるものがなくて死んでしまう生きものは多い」のだと。子ヤギの体は、そんな動物たちを助けることになるのです。動物だけではありません。春になって動き出す虫たちにとっても、残りものが食べものになるのです。
夕方になり、帰りの車の中で、マユは子ヤギのことをただ単に「かわいそう」と思っているだけではないことに気づきます。雪原で見た、生と死がひとつになったような不思議な木と、死んだ子ヤギとを重ね合わせていました。
この本を開くとき、凍てついた北の大地の、厳しくも美しい情景が目に浮かんできます。そこでは、生と死がとても身近です。静かな感動と共に、いのちの儚さと尊さを教えてくれる1冊です。
(C) 加藤 多一 ・ 千葉 三奈子 (画) くもん出版

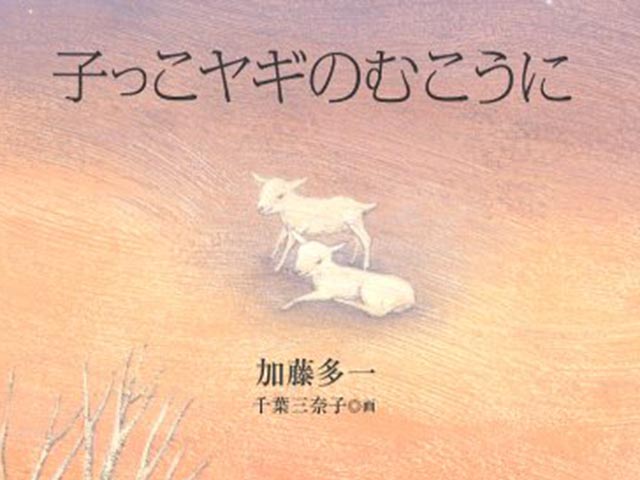
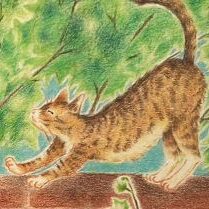
\ コメントくださ〜い /