札幌のシンボルである時計台。かつて時計台に憧れた少年が成長し時計職人となり、時計台を守っていきます。
その想いは息子に受け継がれて…。
札幌時計台の歴史と時計職人の親子の実話を描いた絵本です。
札幌時計台の歴史を語る絵本
明治8年。札幌の東西と南北にのびる広い通りに沿って、外国風の建物が建てられていきます。その中には、北海道大学の前身である札幌農学校もありました。6年後、その校舎のひとつが時計台になったのです。
明治38年のこと。旭川から札幌の親戚宅に遊びに来ていた少年が、時計台に憧れを抱きました。少年は、大人になったらこの時計の機械をいじれるようになりたいと考えます。
その少年の名は井上清さん。清さんはやがて時計職人となり、時計台の近くに時計店を出しました。そして、「時計台のお医者さん」として時計台を守ってきたのです。
昭和20年。太平洋戦争が終わると、荒れていた時計台は修理され、外壁もきれいに塗り替えられました。
昭和25年には、時計台は図書館として利用されていたそうです。時計台のまわりには、旅館や商工会議所、小学校などが建っていたといいます。
この頃、時計の力を振り子からモーターに替えようという話が持ち上がっていたそうですが、清さんは反対しました。
やがて、高齢になった清さんに代わって「時計台のお医者さん」になったのは、息子の和雄さんでした。清さんの時計台への想いは、和雄さんに受け継がれていったのです。
そんな井上さん親子を悩ませる出来事があったといいます。
時計台が作られて85年たった頃。時計台のある中心街は様変わりし、ビルばかりになっていました。そのため、時計台を移転した方がいいという声が上がったのだそうです。
それでも、「時計台は、たてられた場所にあるから、いいのです」と訴え続けた井上さん親子の願いが叶い、市議会で今の場所に残すことが決まったのでした。
札幌時計台は、ビルの谷間に埋もれながらも、誕生したのと同じ場所で、札幌の街の移り変わりを見守り続けているのです。
札幌の歴史的ランドマーク
札幌時計台といえば、言わずと知れた札幌の観光名所のひとつですね。
私が札幌時計台を訪れたのは、初めて北海道へひとり旅をしたときのこと。北海道在住の友人に会った後、せっかくだから時計台を見ておこうと思ったのです。
札幌時計台は、札幌駅を出て徒歩10分ほどの街中にありました。有名観光スポットとして名が知れ渡っているのに、あまり目立たないことが意外だったのを覚えています。
長い歴史を持つ時計台は、人々が日常を送っている中、そこだけ別の空気が流れているかのようでした。赤と白のかわいらしい外観の時計台は、レトロで魅力的です。
時計台が残っているのは、絵本に登場する、長い間時計台を守ってきた井上さん親子の存在と、札幌の人々の熱い想いがあったからこそでしょう。
「大きな時計台 小さな時計台」の作者は、北海道生まれ、札幌市在住のノンフィクション作家、川嶋康男さん、絵は幼少期から北海道で育ち札幌市在住のイラストレーターひだのかな代さんです。
絵本は、2011年、塔時計130年の節目に出版されたそうです。
それからさらに10年以上がたちました。
今なお変わらずに、札幌時計台の手巻きの時計は、鐘の音を響かせています。
絵本のタイトルの意味
絵本を最後まで読んでいくと、「大きな時計台 小さな時計台」のタイトルの意味がよくわかります。
時計台が誕生した当時は、周囲に大きな建物もなく、時計台は目立っていたことでしょう。
それが、時代の移り変わりとともに街が発展し、ビルが建ち並ぶようになると、時計台はその谷間に埋もれるように目立たなくなってしまいました。
「大きな時計台」は、「小さな時計台」になってしまったのです。
でも、井上さん親子が熱意を持って守り続けてきた時計台は決して小さな存在ではありません。
今や札幌時計台は現存する時計台としては日本で最も古いものなのだそうです。
昭和45年には「国の重要文化財」に指定されています。
時計は一部の部品を交換したものの、ほとんど当初の機械のまま正確に時を刻み続けているそうです。現在では手巻きの振り子を使っている時計台は少なく、電気で動いているものがほとんどなのだとか。
絵本の最後には札幌市民憲章が記されています。
「わたしたちは 時計台の 鐘が鳴る 札幌の市民です」
札幌の人々に親しまれ、井上さん親子が守ってきた札幌時計台。いつまでも、札幌の街に鐘の音を響かせ続けてほしいと思います。
(C) 作:川嶋康男 絵:ひだのかな代 絵本塾出版


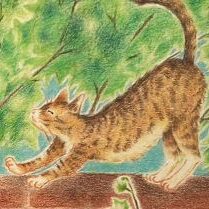
\ コメントくださ〜い /