狩りが苦手で貧しい暮らしを送っていたひとりのアイヌが、唯一得意とするユカㇻで村を救う様子を描いた絵本です。
狩りが苦手なアイヌ
北海道の先住民族であるアイヌの人々は、狩猟や漁、採集で日々の糧を得ていました。この絵本の語り手である男は、狩りが下手なために、貧しい暮らしを送っています。
男には、家族がいました。子どもたちは、いつもお腹をすかせて、狩りに出た父親の帰りを待っています。
そんな男にも、ひとつだけ、得意なことがありました。それは、アイヌに伝わる物語「ユカㇻ」を子どもたちに語って聞かせることでした。
ある日のこと。村に疫病の神がやって来ます。男は「パヨカカムイ」と呼ばれる、病気をまき散らす神によそへ行ってもらうために、お供えをしました。すると、パヨカカムイは、お供え物とともに、どこかへ去って行ったのでした。
その晩、男は夢を見ます。夢に現れたのは、パヨカカムイでした。パヨカカムイは、こう告げます。「あなたのユカㇻがあまりにじょうずなので、病気をまきちらす しごとをわすれ、聞きほれてしまった。」さらに、男がお供え物をしたことに対し「あなたは、よいこころを もっている。」と言うのです。パヨカカムイは、他のところに行って住むことにしたのでした。
パヨカカムイは、去り際に、ひとつの煙草入れを置いていきます。病気がはやった際、この煙草入れを太陽にかざすなら、パヨカカムイはここを避けて通ると言うのです。
夢から覚めた男は、手の中に煙草入れがあるのに気づき、村長(むらおさ)の元へ急ぎます。村長は、男のおかげでパヨカカムイがよそへ行ってくれたことを喜び、男に弓と矢を与えてくれました。
それからは、男は狩りがうまくいき、子どもたちにたくさん食べさせてあげられるようになったということです。
病気をまき散らす神
アイヌでは、動植物や道具など、あらゆるものに魂が宿っていると考えられていました。それらは「神」という意味である「カムイ」と呼ばれています。
人間に災厄をもたらす疫病も、アイヌの人々にとってはカムイでした。それが「パヨカカムイ」です。
パヨカカムイは「ヤチボウズ」という形で現れます。ヤチボウズというのは、湿地帯で見られる植物が盛り上がってできた株のことで、絵本では「タクッペ」と呼ばれています。
それがパヨカカムイであるに違いないと思った男は、恐怖を覚えながらも、「ニマ」と呼ばれる器に魚のしっぽやひれを入れて川岸に行きました。そして、ニマの中身をまき、パヨカカムイに別のところへ行ってくれるよう、お願いするのです。
男の願いは通じ、パヨカカムイは、まき散らしたお供え物とともに舞い上がり、どこかへ飛び去って行きます。
疫病をもたらす神と聞くと、怪物のような恐ろしい姿を想像しますが、パヨカカムイは、あられ模様の着物を着た男性の姿をしています。そして、その姿で、男の夢に現れるのでした。
アイヌの口承文芸ユカㇻ
夢に現れたパヨカカムイは、男が語るユカㇻに聞きほれてしまったと言います。それは、病気をまき散らすことも忘れてしまうほどでした。
文字を持たないアイヌの人々は、多くの物語を口伝えで語ってきましたが、「ユカㇻ」というのもその中のひとつで、英雄叙事詩のことだそうです。
男は、狩りは下手でしたが、このユカㇻを語ることが得意でした。暇さえあれば子どもたちにユカㇻを語って聞かせていました。それを聞いていたパヨカカムイは、村から去るだけでなく、男に贈り物を置いていきます。それは、パヨカカムイが着ている着物の柄と同じ、あられ模様の煙草入れでした。どこかで病気がはやっても、この煙草入れを太陽にかざせば、パヨカカムイはここを避けて通ると言うのです。
パヨカカムイが告げたのは、それだけではありません。ユカㇻの語り方まで教えてくれました。
アイヌの口承文芸は、単なる楽しみにとどまらず、儀式の際にも語られ、またアイヌの人々が知るべき教訓も含まれています。子どもたちに言葉を教える意味もあったそうです。ですから、ユカㇻを上手に語ることができるというのは、狩りと同じくらい大きな意味を持っていたのでしょう。
この絵本はアイヌの昔話が元になっていますが、昔話は「ウゥェペケレ」と呼ばれるそうです。長い間語り伝えられてきた物語は、アイヌ文化研究者のかやのしげる(萱野茂)さんによって、絵本になりました。多くの教訓を含んだアイヌの物語を手に取ることができるのは、とても貴重な経験だと思うのです。
パヨカカムイの物語が伝えること
もちろん、村が救われたのは、この絵本の語り手である男が、ユカㇻが得意だったからだけではありません。疫病の神であるパヨカカムイに敬意を払う、良い心を持ち合わせていたからです。また、パヨカカムイに言われた通り、村長にパヨカカムイの話を伝えました。
村長もまた、男の話を聞くと泣いて喜び、村人たちとともにお酒を作ってパヨカカムイにお供えしたのです。
平和に暮らしていても、時には災厄に見舞われることがあります。疫病や災害は、人間の力ではどうにもならないものです。無力であることを知り、大きな力の前に心をこめてお願いする。そして、守られた時には感謝を忘れない。そんな当たり前のことを、私たちは忘れてしまっているかも知れません。アイヌに伝わる物語は、いつも大切なことを教えてくれます。
この絵本は、アイヌの人々に謙虚な心やユカㇻの大切さを伝える内容ですが、現代に生きる私たちへのもうひとつのメッセージが込められているような気がします。それは、人はみな違うということ。アイヌであっても、狩りが苦手な人はいます。人には得手不得手があり、みながみな、同じようにできるわけではありません。
しかし、絵本の主人公がユカㇻが人一倍上手であったように、好きなこと、得意なことはあるのではないでしょうか。自分にとって大切なことに懸命に、そして楽しみながら打ち込むうちに、道は開かれていくのかも知れません。
「パヨカカムイ」は、アイヌのひとつの昔話として味わう絵本というだけでなく、私たちがこれからを生きるためのヒントも与えてくれると思います。
(C) Komineshoten かやのしげる 文/いしくらきんじ 絵

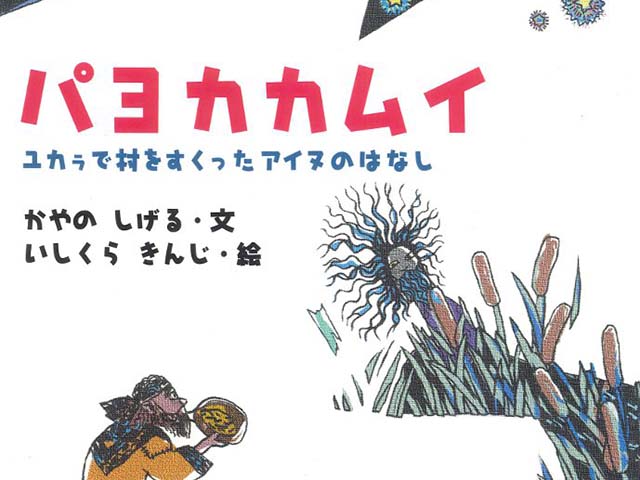
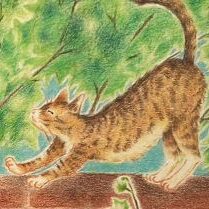
\ コメントくださ〜い /